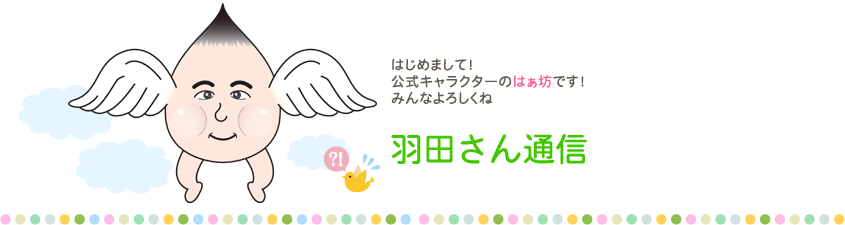
日本の無痛分娩を取り巻く話題 JALAの話
2019年12月7日 土 雪い
いよいよ今年も終わりが見えてきた12月。
気候はしっかり冬モードに突入し、景色は真っ白く、道路も見えなくなりました。
これから雪に閉ざされた長い冬が始まるな~
12月といえば忘年会
当院は21日土曜日の予定ですが、「院長の余興」として、1年間のまとめスライドを毎年発表しているので、またぞの準備もちょっとずつ気になり始めたところです![]()
さて、前回のブログで産科麻酔学会に行ってきた話を書きましたが、今回は日本の無痛分娩を取り巻く話題についてちょっと書きたいと思います。
2017年4月に日本産科婦人科学会学術総会で
「妊産婦死亡症例検討評価委員会」より、2010年から2016年までの間の妊産婦死亡298例のうち13例で無痛分娩が行われていることを踏まえ、無痛分娩を行う際は、適切に対応できる体制を整えるべきとの緊急提言 (※実際には271例中14例)
が発表されたことを受け、一部マスコミが「無痛分娩は危険」との印象を与えるセンセーショナルな報道をしました。
これで一時、産科関係機関と患者さんの間でちょっとした衝撃が・・・。
JALAは2019年3月に始動して、無痛分娩をより安全に行うために、無痛分娩を行っている施設をホームページ上でっ紹介したり、施設向けに講習会を企画したりしていますが・・・
9月の初旬に日本産婦人科医会という産婦人科医の集まりの中央の人たちがやってきて、今の産婦人科を取り巻く環境や医療政策についてお伝えしてくれる北海道ブロックの集まりがありました。
その中で「無痛分娩をやっている施設はJALAに登録をしてください」との広報があったので当院も一応、参画希望の申し込みをしました。
すると、無痛分娩の施行施設として認めてほしかったら、産婦人科医で麻酔科免許を持っている人は産婦人科医として表記しなさい。
ホームページを書き直しなさいなど、ちょっとめんどくさい要求が送られてきまっした。
当初、無痛分娩を安全に「広める」組織だと思っていたのですが、産科麻酔学会で、JALAの会長の講演を聞いていたら、どうやら組織の中のルールを守らないなら「無痛分娩やりにくくさせますよ」・・・的なニュアンスなんですよね。
講習会も全国でやるわけではないし、北海道で小さな分娩施設をやってたら参加できませんよ。ホント
2017年の「無痛分娩で事故」報道で、一時社会的にも注目されて、危険なものの様な誤った認識を正すのが、責任ある組織(JALA)の役割だと思っていたのですが、厚生省やマスコミの言いなりになって、「危険だから厳しくしますね」という論調にのっかててたらせっかく良い医療も中枢がダメだと台無しになってしまうと思います。
日本を動かす組織ならしっかりリーダーとしてやってほしいな・・・
そう思って、先月の産科麻酔学会に参加してきました。
しっかり質問と意見できたので目的は達成しましたが、これからも良い医療を提供できるように精進しようと思います![]()
コメントを残す